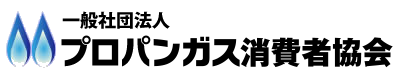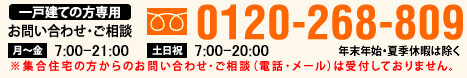格安セールスが信用できない理由
格安価格ではガス会社として赤字になります
プロパンガスは90%以上をカタール、アブダビ、サウジアラビアなど中東諸国を中心に輸入しています。その輸入価格に運賃、販売管理費、利益などの諸経費を上乗せして利用者への販売価格が決まります。
その結果、250円以下などの格安価格で販売すると経費倒れとなり、格安価格で売れば売るほど赤字になってしまうのです。
しかもセールスマンにコミッションを払う必要があります
基本的に、プロパンガスの訪問セールスマンの多くはガス会社の社員ではなく、新聞の拡張員のような契約会社の営業専門員です。
彼らは特定のガス会社と業務提携をして訪問セールスを行います。例えば単価250円で受注した場合はコミッションは3万円もらえるが、230円の場合は1万円下がってしまい2万円になったりします。
つまりセールスとしては注文をもらいやすくなる分赤字幅は拡大するので、コミッションも減ってしまう訳です。
結局値上げでカバーする必要があります
プロパンガス会社としては、赤字価格での販売に加えさらに契約セールスマンへのコミッションまで負担する訳です。これではお客様が増えれば増えるほど経営は窮地に陥ってしまうので、値上げは必然なのです。
値上げは簡単です
普通値上げをするのは簡単ではないですが、プロパンガスの場合はすごく簡単にできます。まず認可の必要な公共料金である都市ガスと違いプロパンは自由料金ですから、いつでも好きな時に値上げできます。
また、法律では値上げする際には、利用者への告知が必要ですが、告知なしで値上げしているガス会社は少なくないと思われます。要は知らないうちに値上がりしてしまったということが頻発します。
さらに、産ガス国では毎月輸出価格を決めますが、買い手の意向に関係なく売り手の都合で決めるので、需要期の秋から冬になると必ずといっていいくらい値上げします。
これに伴い、日本のプロパンガス販売会社は当然すぐに販売価格を一斉に値上げします。格安で販売した会社もこれに歩調を合わせることで簡単に値上げできます。
また、産ガス国では春から夏にかけて輸出価格を値下げしますが、プロパンガス販売会社はこの動きに対しては反応しないか、値下げの時期を意図的に何ヶ月も遅らせるか、40円上げた会社は20円だけ下げたり、10円ずつ3回下げたり、さまざまなテクニックを使います。格安セールスの会社は当然値下げはしない傾向にあります。
当協会に寄せられる相談で多いのは、230円などの格安価格で契約したあと、年に100円くらいずつ上がっていくケースです。中には半年で150円も上がった例があるので、充分にご注意しましょう。
参考になるページ